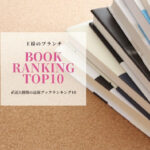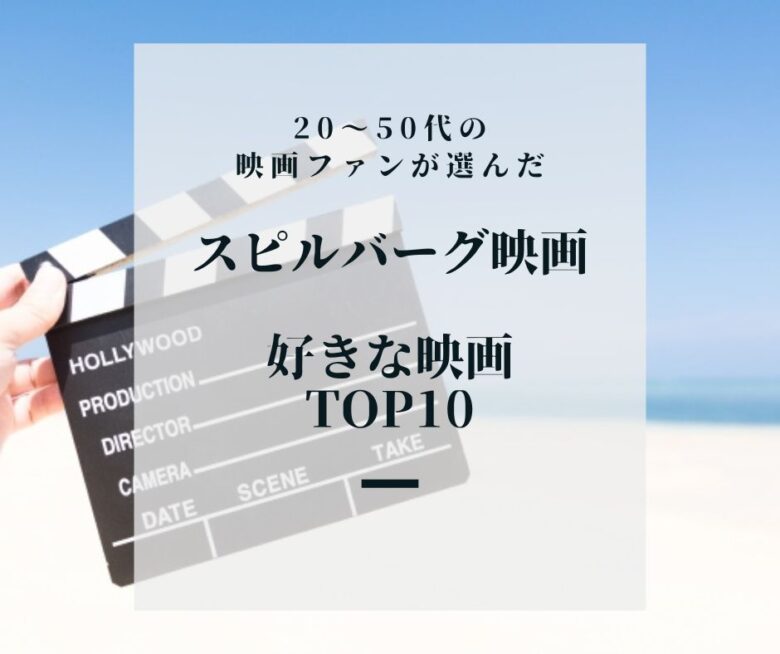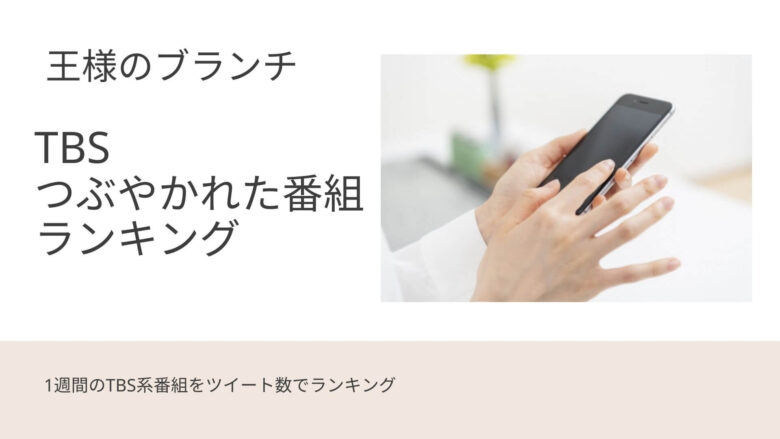江戸時代 町民の「水道料金」何で決めた?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう5月15日は「水分補給の日」です。
飲み水として使うことができる水道は、江戸時代からありました。
徳川家康は江戸幕府を開くときに、家臣に水道整備を命じています。
東京の文京区に水道という地名がありますが、ここは最初に完成した小石川上水という水道が由来の地名です。
そんな江戸時代の水道にも水道料金がかかったのですが、水道メーターがない時代にどうやって料金を決めたと思いますか?
今日は江戸時代の町人の水道料金は何で決まったかという問題です。
江戸時代 町民の「水道料金」何で決めた?
青 -玄関の幅
赤 -住人の数
緑 -月火木金日はOK
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -玄関の幅
| <今日の緑のボケ> 「すいどうりょうきん」ではなく「すいど(水土)りょうきん(両禁)」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
今日の問題は、町人に限定していますが、もちろん武士も水道料金を払っていました。
実際には武士と一言で言っても、身分がいろいろ分かれていました。
その身分に応じて、今でいう給料である俸禄が決まっていたので、その額に応じて水道料金も決まっていました。
一方、町人も通りに面したところに自分の持ち家がある人と、長屋で暮らす庶民は区別されていました。
長屋とは一棟の家を区切って、いくつかの世帯が家賃を払って住んでいる形態の建物です。
外に井戸があって、そこに水道が引かれていました。
こうした長屋では、家賃に水道料金が含まれていて、大家さんがまとめて支払っていました。
長屋の大家さんにとっては、火事と水道料金の支払いが悩みの種だったようです。
そして、表通りに面して家があるような町人には、玄関の間口の幅を基準に水道料金が課されていました。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法