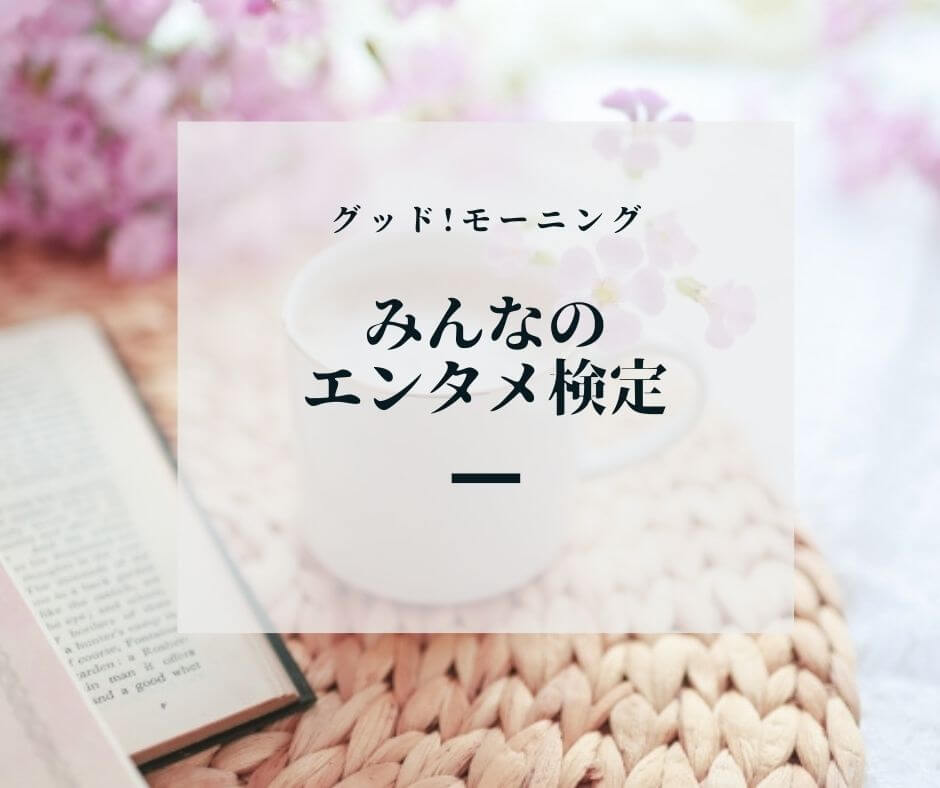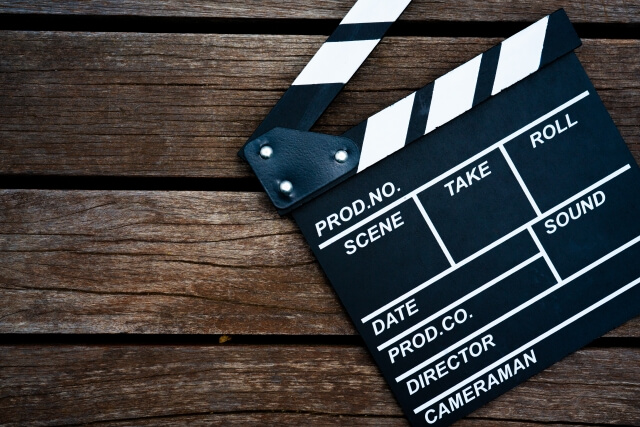「長広舌」誰の姿に由来?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう9月10日は、仙台名物「牛タンの日」です。
戦後に仙台で生まれて、名物として認知されるようになったのは昭和50年代だと言われています。
牛タンは牛の舌の肉ですが、舌がつく言葉で熱いものを食べたり飲んだりできないことを「猫舌」と言います。
この言葉、江戸時代から使われていた言葉です。
また長々と喋り続けることを、長く広い舌と書いて「長広舌をふるう」という言葉があります。
今日はこの「長広舌」は誰の姿に由来するかという問題です。
「長広舌」誰の姿に由来?
青 -妖怪
赤 -仏
緑 -違うそうじゃない
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -仏
| <今日の緑のボケ> 「ちょうこうぜつ」ではなく「ちゃう こうです」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「舌」が付く言葉には、こんな言葉もあります。
「二枚舌」は、矛盾したことを言うこと、嘘を言うことを指します。
「舌先三寸その」は、口先だけで心がこもらない言葉という意味です。
これはよく「口先三寸」と言ってているのを聞きますが「舌先三寸」が正しいです。
共通するのは、悪いイメージです。
問題の「長広舌(ちょうこうぜつ)」も、「長広舌をふるう」と長々と喋りたてることを批判的に使うことが多い言葉です。
この言葉の由来となった「舌」は、広くて長く しかも柔らかいために、その顔を覆うことができたといいます。
伸ばすと髪の際や耳にまで達するといわれるその持ち主は仏です。
これ、実は恐ろしい姿というわけではありません。
仏の説く言葉が広く響く渡ることを、広く長い舌の姿で表しているのです。
元々は、広いが先の「広長舌(こうちょうぜつ)」と言っていて、とうとうと説く巧みな弁舌 雄弁と、決して悪い意味ではなかったのです。
これがなぜか順番が変わって「長広舌」は、長い弁舌を批判的にとらえた言葉になってしまったのです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法