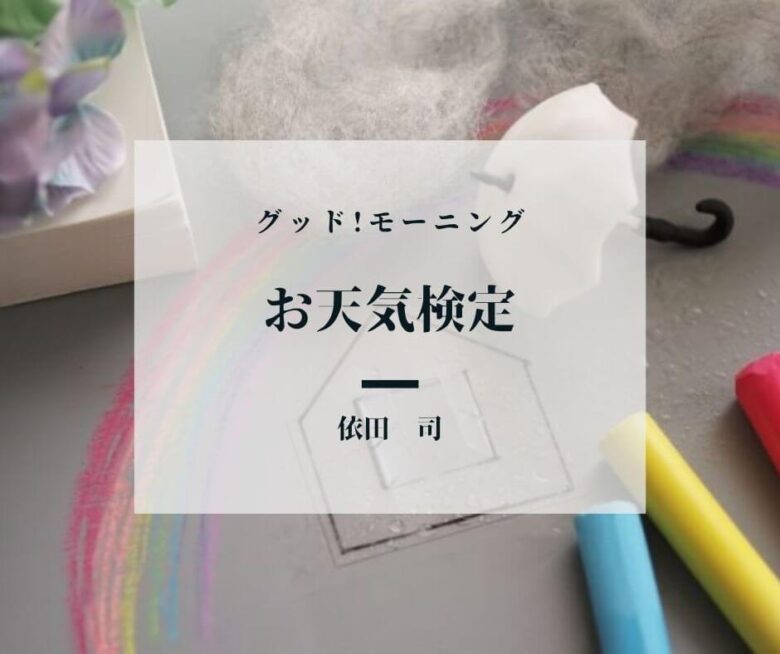「樽廻船」の名前の由来は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょうは「海の日」です。
元々は7月20日でしたが、2003年から7月の第3月曜日になりました。
なぜ「海の日」は7月20日に定まったかには理由があり、1876年に北海道・東北の巡航を終えた明治天皇が船で横浜港に戻ってこられた日なのです。
その時の船の名を「明治丸」と言って、今も残っていて見学することができます。
この明治丸はイギリスで造られ鉄で出来ていますか、江戸時代の船は木材で作られていました。
江戸時代は海運がとても発達し、「菱垣廻船」「樽廻船」という船が活躍しました。
「菱垣廻船」は船の側面にひし形の模様の名前が由来ですが、「樽廻船」の名前の由来は何でしょうか?
「樽廻船」の名前の由来は?
青 -酒樽専用
赤 -樽のような形
緑 -刺身追加する?
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -酒樽専用
| <今日の緑のボケ> 「たるかいせん」ではなく「足る?海鮮」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「菱垣廻船」と「樽廻船」、先に生まれたのは「菱垣廻船」です。
最初の「菱垣廻船」は、1619年 大阪・堺の商人が木綿や酒などを江戸に運びました。
多いときは160隻もあったそうです。
そんな「菱垣廻船」ですが、その後 一部の人が不満を募らせるようになったのです。
船に荷を積む場合、重い荷を積み込みますが、「菱垣廻船」が運んだ木綿・酒・薬の中で一番重いのはお酒でした。
ですから酒は最初に積んで、最後に下ろしていました。
荷物の上げ下ろしにあまりに時間がかかると、酒が傷んでしまうこともあったそうで、酒の荷主が不満をためていました。
そんなこともあって、お酒の樽を専門に運ぶ船が誕生し「樽廻船」と名付けられました。
「樽廻船」は荷受けから届けるまでのスピードが速く、次第に酒以外の荷物も集まって来るようになったそうです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法