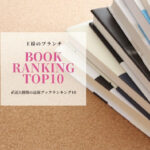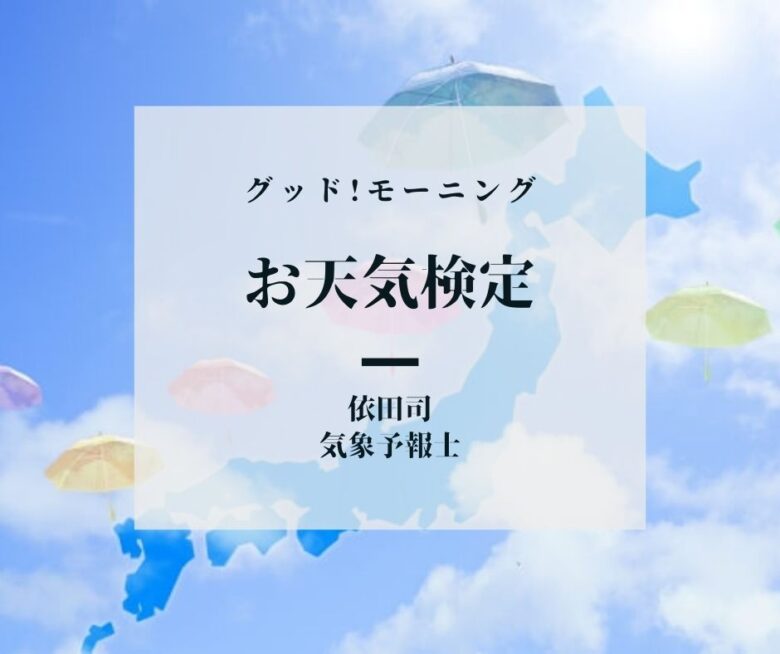「勘亭流」の書体が太い理由は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう4月10日は、日付の語呂合わせで「フォントの日」です。
「フォント」とは、文字の書体のことです。
日本語の書体で、新聞などに広く使われているの「明朝体」です。
中国・明朝の時に日本に伝来したので、明朝体と呼ばれるようになったと言われているようです。
そして、最近注目されている書体が「UDフォント」です。
UDとはユニバーサルデザインのことで、誰にでも読みやすいデザインということで広まっています。
「勘亭流」と呼ばれる書体は、落語とか歌舞伎の看板や番付などに使われています。
勘亭流は肉太で丸みを帯びているのが特徴ですが、今日はこり「勘亭流」の書体は太い理由は何かという問題です。
「勘亭流」の書体が太い理由は?
青 -空席をなくす
赤 -懐が肥える
緑 -ドラゴンの品定め
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -空席をなくす
| <今日の緑のボケ> 「かんていりゅう」ではなく「かんてい(鑑定)りゅう(竜)」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「勘亭流」の文字が使われ始めたのは、江戸時代中期ではないかと言われています。
その江戸時代に始まり発達した劇といえば歌舞伎です。
当時、中村座という劇場があって、その依頼で書かれたのが、のちに「勘亭流」と呼ばれる書体でした。
「勘亭」という号を持つ、岡崎屋勘六が書いたのが始まりだと言われています。
「勘亭流」の太すぎて読めない文字は、「読めないくらいのものを読むのが通だ」という解釈も当時あったようです。
文字が太くて隙間がほとんど空いていない勘亭流は、客が大勢入って席に隙がないようにという願いが込められた文字です。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法