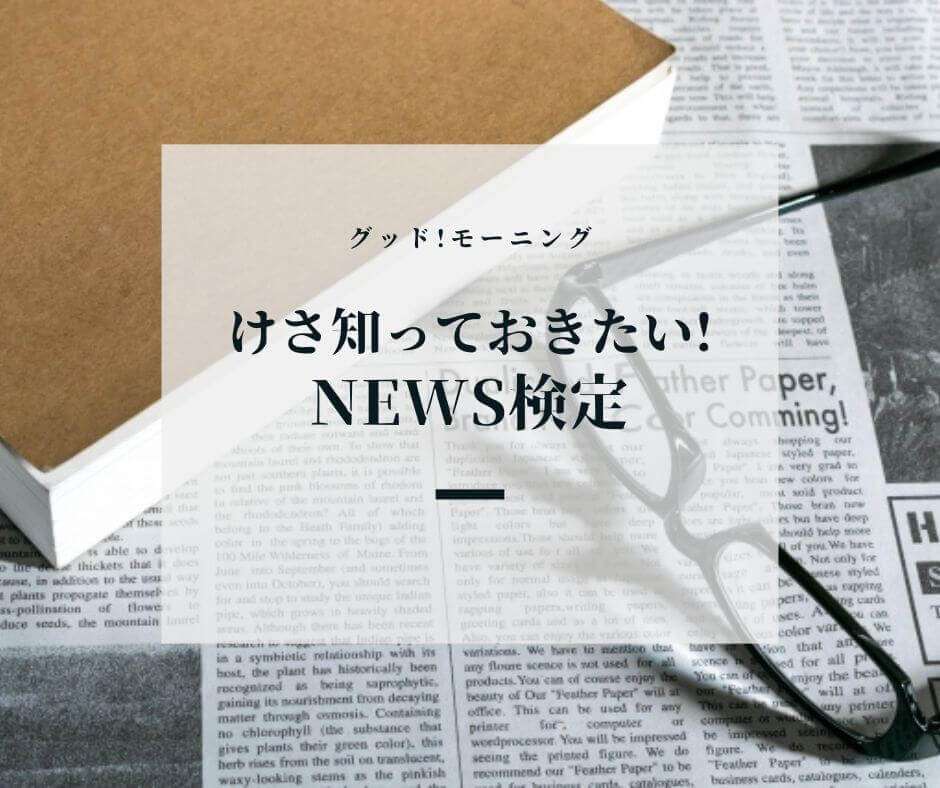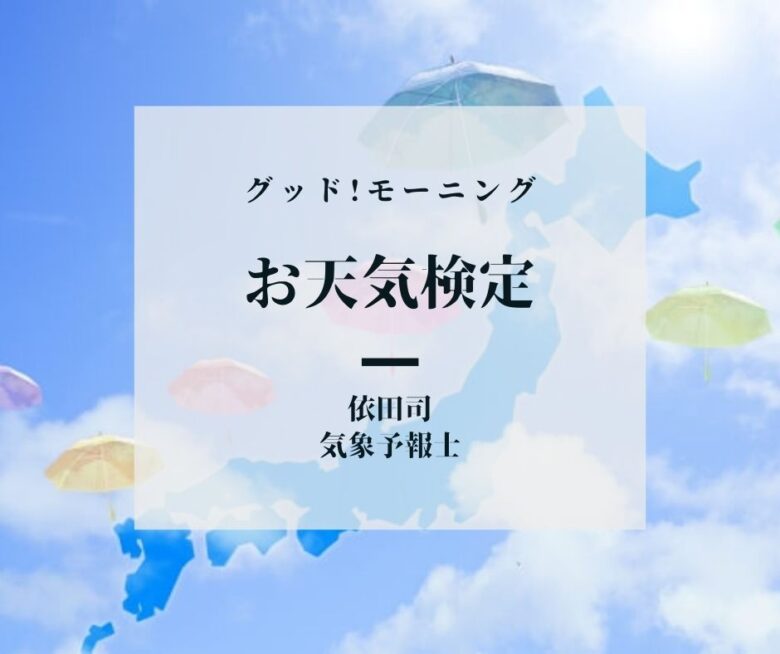「とび職」の由来は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう4月9日は、日付を「しっくい(漆喰)」と読めます。
漆喰は壁に使われます。
壁を塗る職人さんを「左官」と言いますが、なぜ左という字を使うのでしょうか?
左の字を使うようになったのは江戸時代からで、当て字です。
「左官」は上官を補佐する役職を指していました。
「左官」を辞書で引くと、"宮中の修理に、仮に木工寮の属(さかん)として出入りを許したことからいう"と説明されています。
木工寮とは、古代の律令制度の時代に宮中の造営や木材の準備を担当する役所のことだそうです。
このように古くからある「左官」という職業ですが、建設に関わる職業に「とび職」もあります。
土木や建築工事をする方ですが、今日はその「とび職」は何に由来する言葉かという問題です。
「とび職」の由来は?
青 -職人の道具
赤 -鳥の飛び方
緑 -無断退職に驚く
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -職人の道具
| <今日の緑のボケ> 「とびしょく」ではなく「飛びショック」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「とび職」は、特に高いところで足場を組んで仕事をするような方を指す言葉です。
鳥の鳶(とび)には「鳶が鷹を生む」という言葉がありますが、親よりも子どもの方が優れているときに使われます。
鳶も鷹の一種で、"ぴーひょろろ"と鳴いて円を描くように飛びます。
そして「とび職」の「とび」はこの鳥が由来です。
職人が使う「鳶口」という道具の金具部分が鳶のくちばしに似ています。
この道具で、火事のとき延焼を防ぐため、家を壊すのに使ったり、物を引っ掛けて運んだりするのに使われました。
そして、この道具を使う人のことを江戸時代に「鳶の者」と呼ぶようになり、その後「とび職」というようになったと言われています。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法