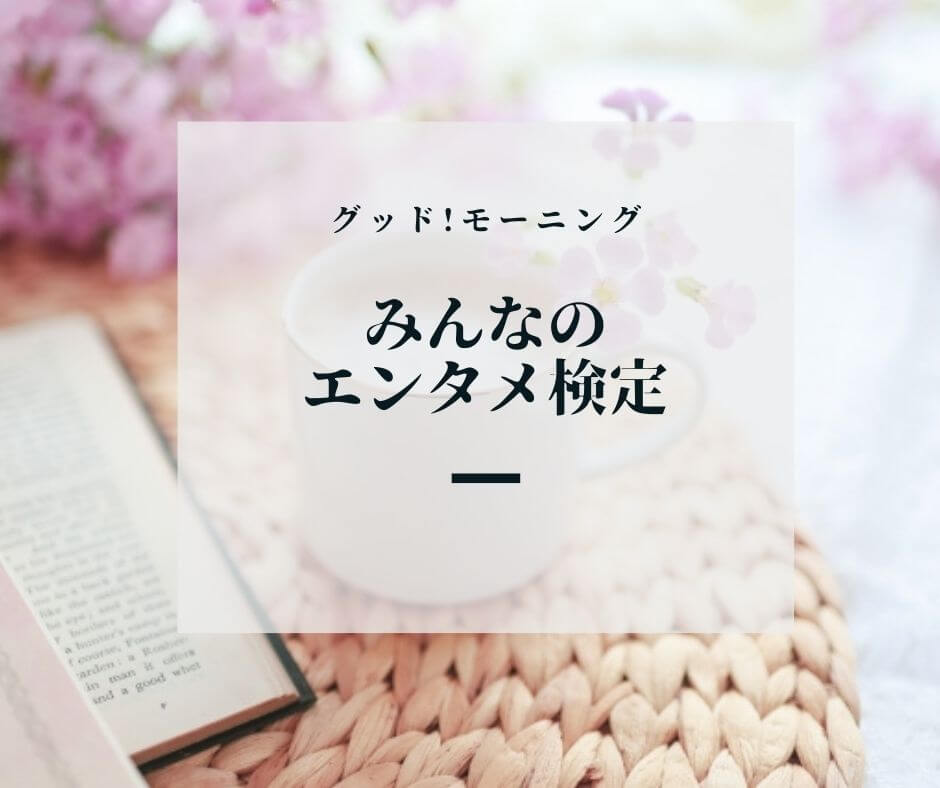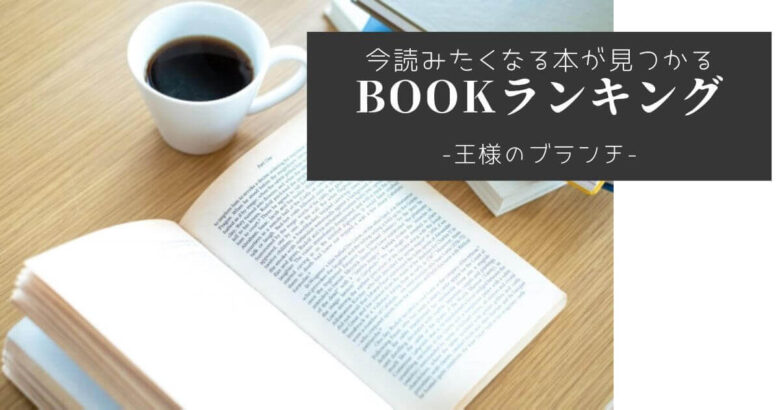「江戸の花見」で流行ったものは?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
桜の季節ですが、花見は大勢でワイワイ楽しむ大勢派ですか?それとも一人で静かにというひとり派ですか?
平安~鎌倉時代の僧侶・西行はひとり派だったようで、こんな歌を残しています。
「花見にと 群れつつ人の 来るのみぞ あたら桜の とがにはありける」
花見に大勢がやってくることだけは惜しむべき桜の罪であるという内容です。
なかなか面と向かっては言えませんから、こうやって歌にしたのかもしれないです。
さらに、桜好きの西行はこんな究極の願いを歌に込めています。
「願わくは 花のしたにて 春死なん その如月の 望月の頃」
如月の望月のころ頃というのは、お釈迦様が入滅した日とされる2月15日を指しています。
この日に死にたいと西行は願ったのですが、実際には2月15日の翌日、2月16日に亡くなりました。
当時は陰暦ですから、桜の下でという願いはかなったのかもしれないです。
今日は日本人が好きな「花見」について、江戸で流行ったものはという問題です。
「江戸の花見」で流行ったものは?
青 -崖から皿を投げる
赤 -桜の下で散髪
緑 -その肉食べていいよ
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -崖から皿を投げる
| <今日の緑のボケ> 「えどのはなみ」ではなく「え?どのハラミ?」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
東京の北区に飛鳥山公園という花見の人気スポットがあります。
ここに桜が植えられたのは江戸時代です。
今日の答えは、飛鳥山の花見で特に流行ったのですが、その理由はここが高い場所だったことにあります。
厄除けなどで崖から素焼きの小さな皿を投げる土器(かわらけ)投げというものでした。
飛鳥山の崖の下に今は線路が走っているのですが、、その線路が出来たときにそり土器投げを禁止する決まりができたそうですから、長い間楽しまれてきました。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法