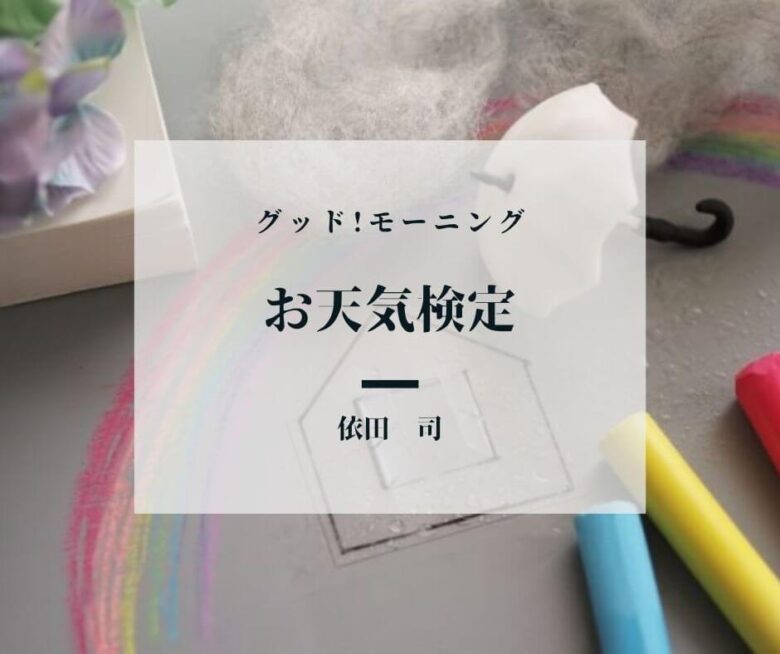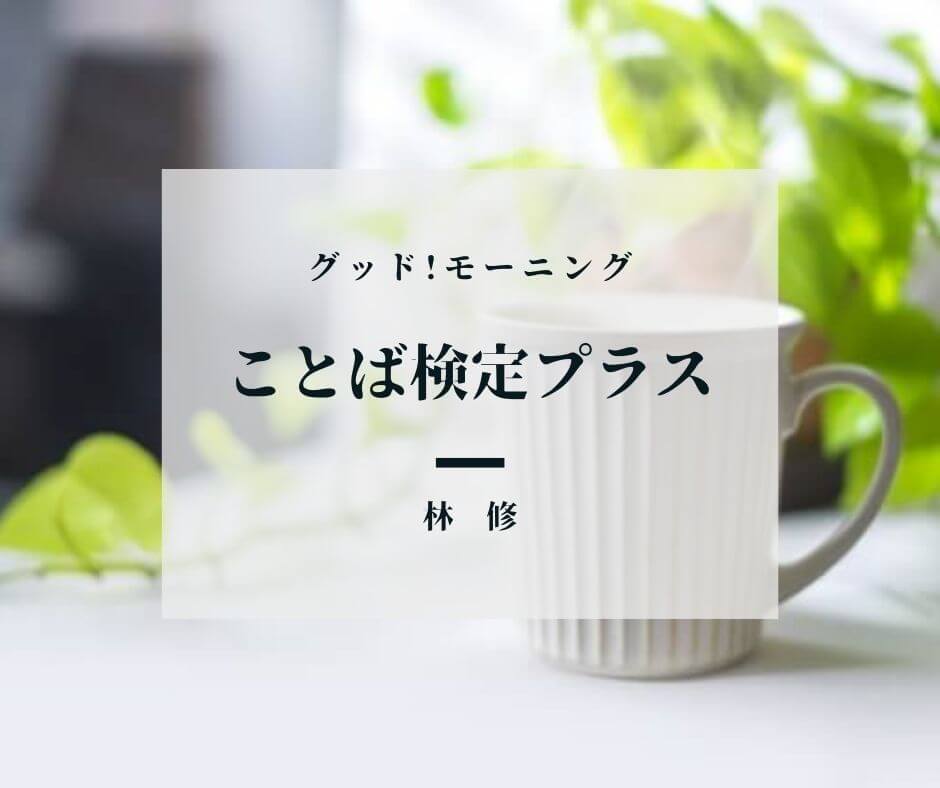「似て非なるもの」の由来は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう2月5日は、日付の語呂合わせで「ふたご」となるので、双子の話題です。
そんな双子の中でも遺伝子情報がほぼ同じだと、一卵性双生児と呼びます。
99.99%のDNAが同じで、最近までDNA鑑定して判別できなかったそうです。
そんなDNAの塩基配列、つまり並び順が98.8% 人と同じ動物がチンパンジーです。
この違いは、馬とシマウマより小さいそうです。
DNAは似ているものの、人とチンパンジーを見分けられない人はいないですよね。
というわけで、今日は「似て非なるもの」という表現の由来は何かという問題です。
「似て非なるもの」の由来は?
青 -欲しいもの
赤 -にくむもの
緑 -エビ・カニ
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -にくむもの
| <今日の緑のボケ> 「にてひなるもの」ではなく「似て緋なるもの」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「似て非なるもの」は、似ているけれども異なるという意味です。
例えば、見た目が穀物の苗にそっくりな雑草があったら、それは似ているけど違うものです。
この例は、中国に思想家・孔子が「似て非なるもの」はどういうものかというのを、説明する時に話したものとして出てきます。
ー「孟子」から
孔子曰く、似て非なる者を悪(にく)む。
莠(はぐさ)を悪(にく)むは、其の苗を乱るを恐るればなり。
さらに、こう続きます。
口先の上手なものを憎むのは、その言葉がいかに義を装って紛らわしい。
この「似て非なるもの」という表現は、得があるものに似ているものの実際そうではなくて、紛らわしい偽善者を非難する文脈で出てきています。
ちなみに、ニセモノのことを「似非」といいますが、似て非なると漢字で書きます。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法