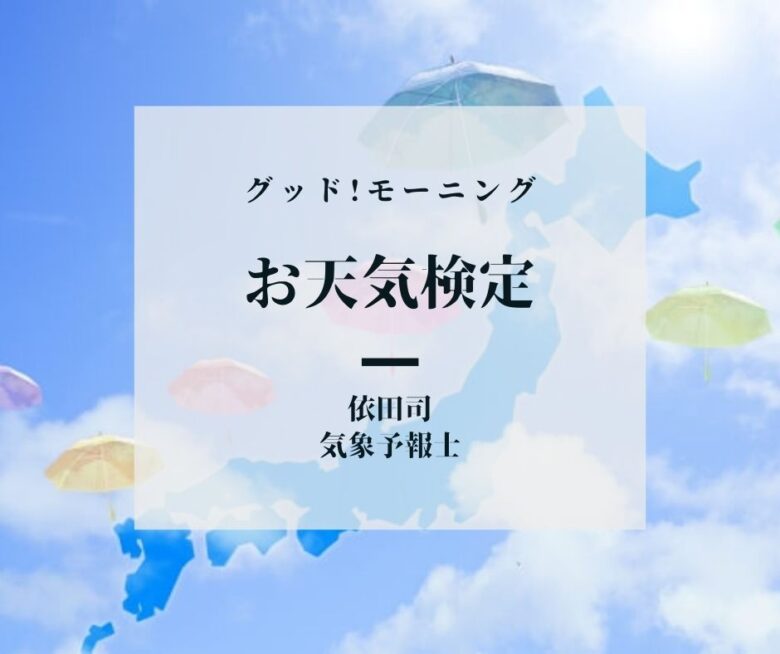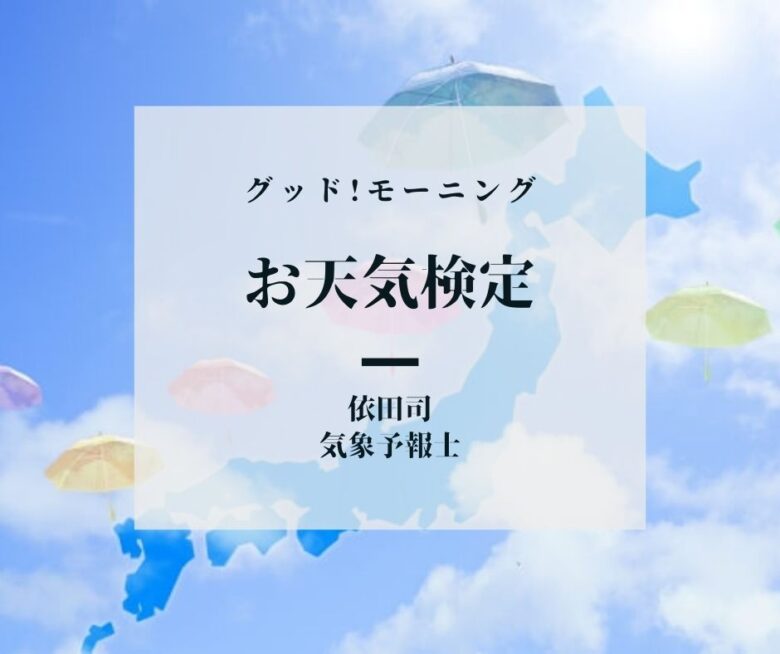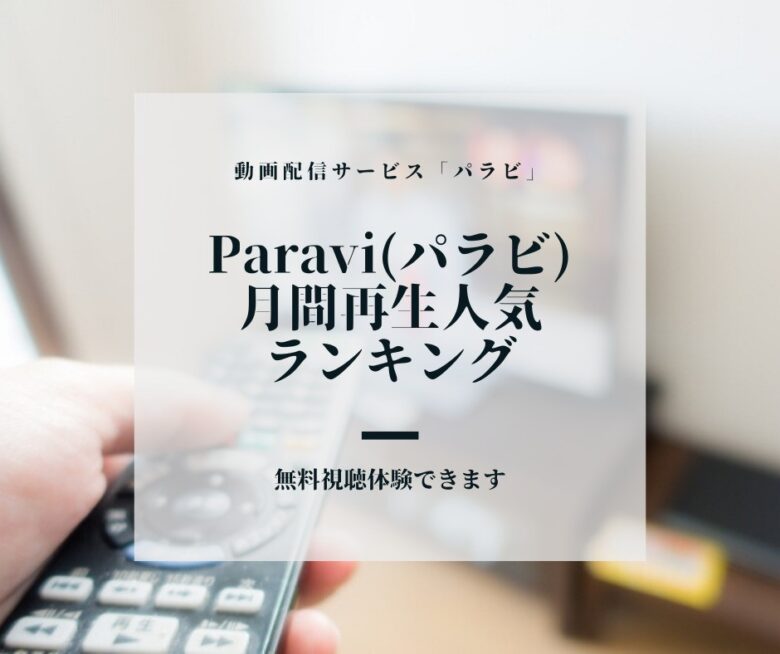「獺祭」の意味は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう9月9日は「重陽(ちょうよう)」 菊の節句です。
松尾芭蕉はこんな句を読んでいます。
「草の戸や 日暮れてくれし 菊の酒」
重陽に菊の酒を飲む風習があったのです。
桃の節句は女の子の成長を祝い、端午の節句は男の子の成長を祝う風習です。
菊の節句で飲む酒は、長寿を祝う酒です。
これは芭蕉の晩年の句で、「草の戸」はわびしい住まいのことですが、日が暮れてからとはいえ、そこへ弟子の一人が菊の酒を持ってきてくれたと詠んだ句です。
「獺祭(だっさい)」は大人気の山口のお酒ですが、これと同じ「獺祭」が付く「獺祭書屋主人」と称した明治の俳人は正岡子規です。
今日はこの「獺祭」という言葉の意味は何かという問題です。
「獺祭」の意味は?
青 -酒を飲む
赤 -資料を広げる
緑 -モノクロ
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -資料を広げる
| <今日の緑のボケ> 「だっさい」ではなく「奪彩(だっさい)」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
正岡子規は、明治時代の俳句界に革新をもたらしたと言われています。
当時、松尾芭蕉をやたらと崇拝する風潮があり、子規はそれを批判し、大きな衝撃を与えたのです。
もちろん、芭蕉の句で高く評価した句もあったのですが、欠点もあると子規は指摘したのです。
そして、過去の焼き直しではなく、新鮮な着想を持つべきだと俳句の革新を訴えたのです。
これは何かを批判するには、その前にやるべきことがあります。
相手のことを徹底的に調べないと、まともな批判はできないです。
子規は過去の膨大な俳句作品を集め、その分類に没頭したといいます。
こうして書いたのが「獺祭書屋俳話」という連載です。
この「獺」という字は、カワウソのことでカワウソはとった魚を並べる習性があります。
これを、まるで魚を祀っていると例えた言葉が「獺祭」です。
それが転じて、詩文を作るのに資料を広げ散らかす意味になりました。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法