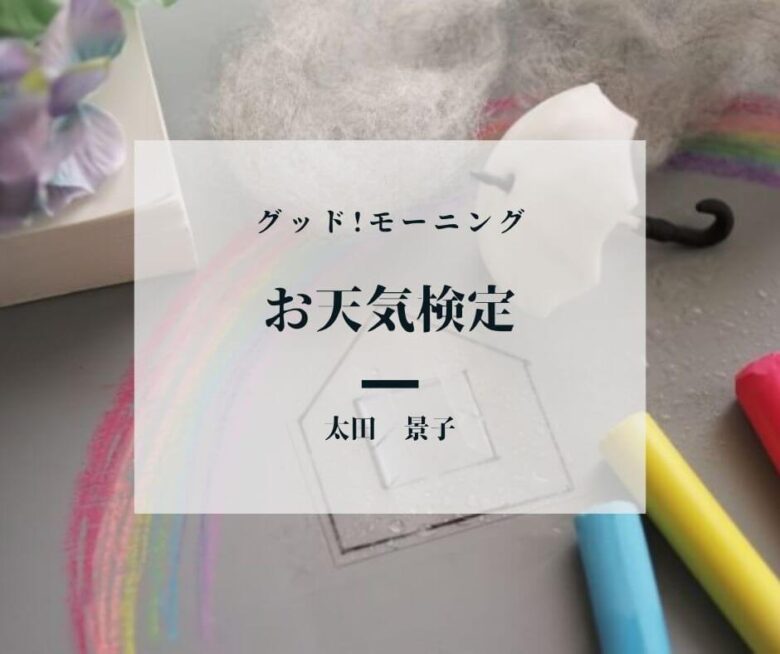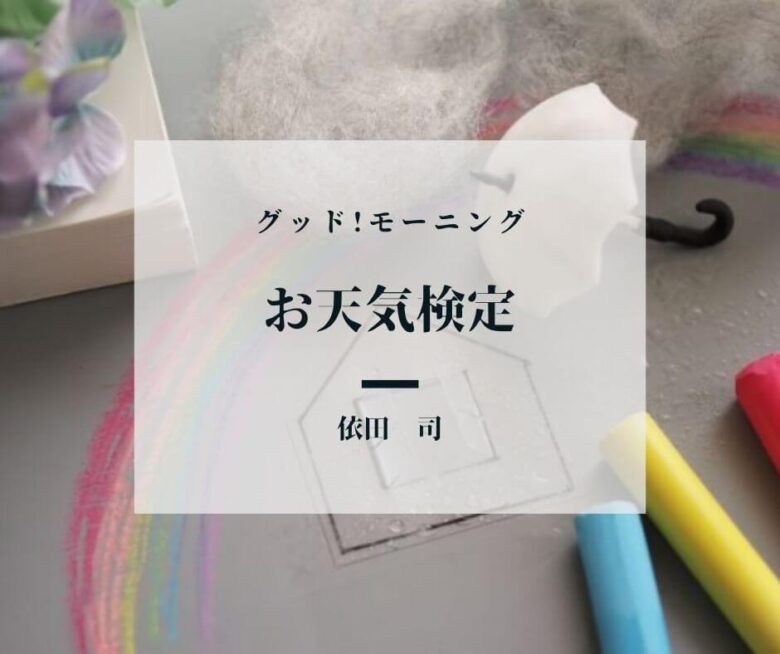「魚心あれば水心」意味は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう8月15日は「刺身の日」です。
室町時代の儒学者の日記「康富記」に、今と漢字は違うのですが「鯛、指身居之」と刺身が登場する日に由来するそうです。
この日記には鯛が出てくるのですが、江戸時代に書かれた食の百科事典「本朝食鑑」には、鯛について「鯛は本朝鱗中の長」と書かれています。
鯛に限らず魚を食べる頻度が高かったようで、江戸っ子について、当時の儒学者は「江戸繁昌記」で「常に言ふ 三日肉食せざれば骨皆離ると」と書いています。
魚を3日食べなければ、骨がバラバラになるというのです。
ちょっと大げさなような気もしますが、江戸っ子たちがどれだけ魚が好きだったかが伝わってきます。
今日はそんな「魚」が入った言葉から、「魚心あれば水心」の意味は何かという問題です。
「魚心あれば水心」意味は?
青 -話さなくても通じる
赤 -相手の態度で決まる
緑 -労うも失敗複数指摘
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -相手の態度で決まる
| <今日の緑のボケ> 「うおごころあればみずごころ」ではなく「おぅご苦労 あれはミスごろっこ(5,6個)」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「魚」と「水」が入った言葉には「水魚の交わり」という慣用句もあります。
親密で離れがたい友情や交際を指しています。
ことばの由来は「三国志」にあり、三国時代の英雄で蜀の建国者・劉備が、三顧の礼で迎えた天才軍師・諸葛孔明が関係しています。
劉備が、諸葛孔明と自分は「水と魚のように切れない間柄」だと説明したエピソードが由来です。
一方、「魚心あれば水心」ですが、元は「魚、心あれば 水、心あり」という形だったとみられています。
魚と水を擬人化したような表現で、「水魚の交わり」と似て、"魚に水と親しむ心があれば、水もそれに応じる心がある"ということから、相手が自分に好意を持てば、こちらもそれに応じる用意があることを言います。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法