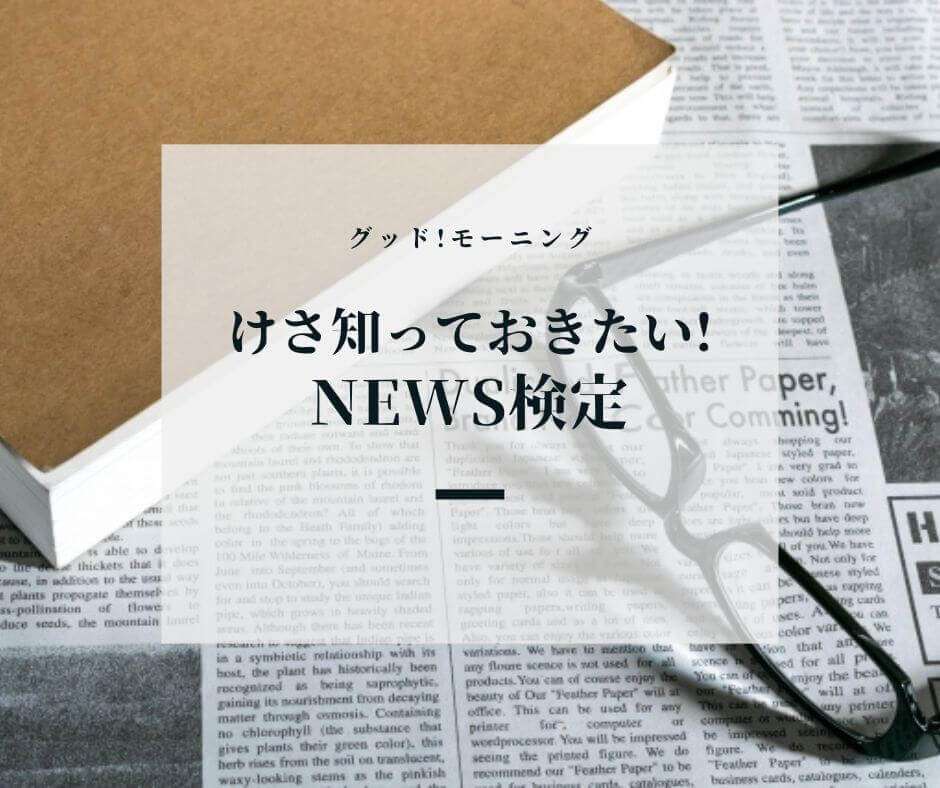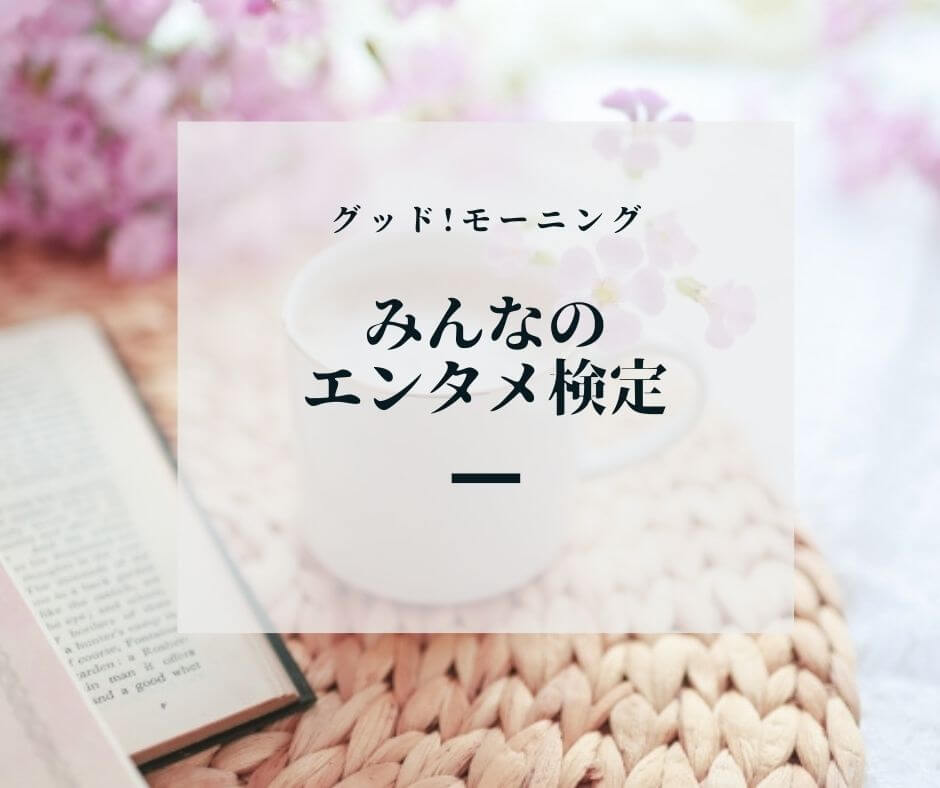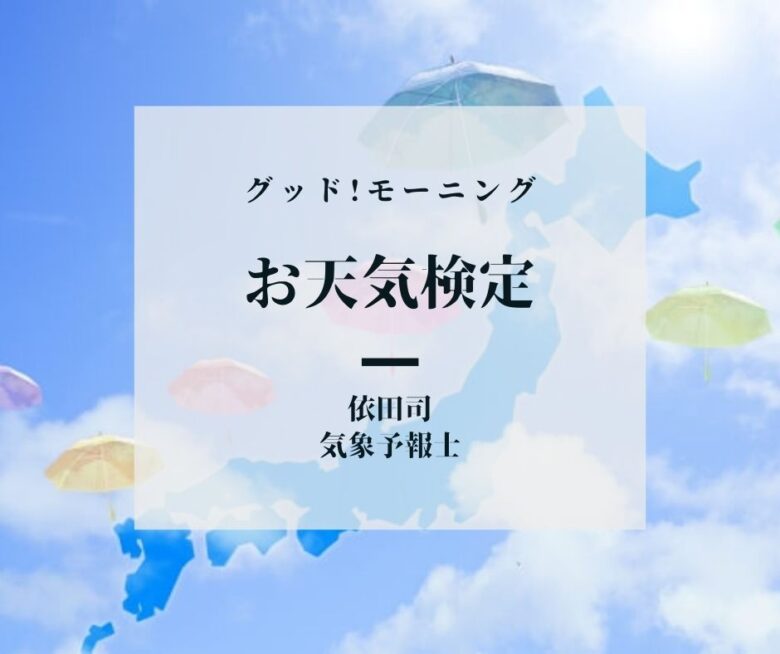元々の意味が「鳥に関係」するのは?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
5月10日から、野鳥を大切にと呼びかける愛鳥週間(5/10~5/16)が始まっています。
動物言語学者の鈴木俊貴さんによると、四十雀(しじゅうから)は鳴き声を言葉として使ったり、それを組み合わせて文章を作ったり、さらに翼でジェスチャーをしていることまでわかってきました。
そのジェスチャーとは、翼を小刻みに震わせる動作だそうです。
四十雀は一夫一妻の鳥で子育ても夫婦が協力するのですが、エサをひなに運ぶとき巣箱の入り口が狭いので「お先にどうぞ」という意味で羽を震わせるそうです。
今日は、元々の意味が「鳥に関係」する言葉はどれかという問題です。
元々の意味が「鳥に関係」するのは?
青 -ふるまう
赤 -もてなす
緑 -ぜひラストで出演を
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -ふるまう
| <今日の緑のボケ> 「とりにかんけい」ではなく「トリに歓迎」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「ふるまう」と「もてなす」に共通する意味は「ごちそうする」です。
「ふるまう」に「ごちそうする」の意味ができたのは鎌倉時代からでした。
その前は、ある動作をしたり態度をとったりする意味で「ふるまう」は使われていました。
馴れ馴れしく振る舞うなどの使い方です。
語源は「翔」という字が関係しているとされています。
この「翔」という字は、平安時代に作られた漢和辞書でひくと読み仮名が「ふるまう」と書いています。
「ふるまう」の元の意味は、鳥がのびのびと羽を動かして飛び回ることだとされています。
漢字だと、今は「振る舞う」と書きますよ。
その後、これを人間に当てはめ、自分の意思に基づき行動をとることを「振る舞う」というようになったと考えられています。
さらに、格式ばった行動をとるという場合も「振る舞う」というようになり、そうした格式にのっとった人付き合いは、接待が付きものであることから「ごちそうする」という意味も生まれたと考えられています。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法