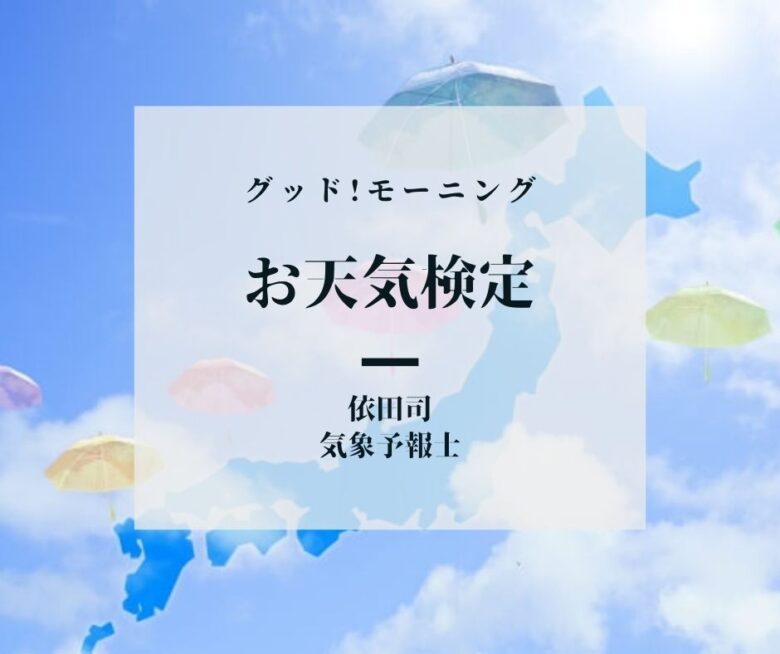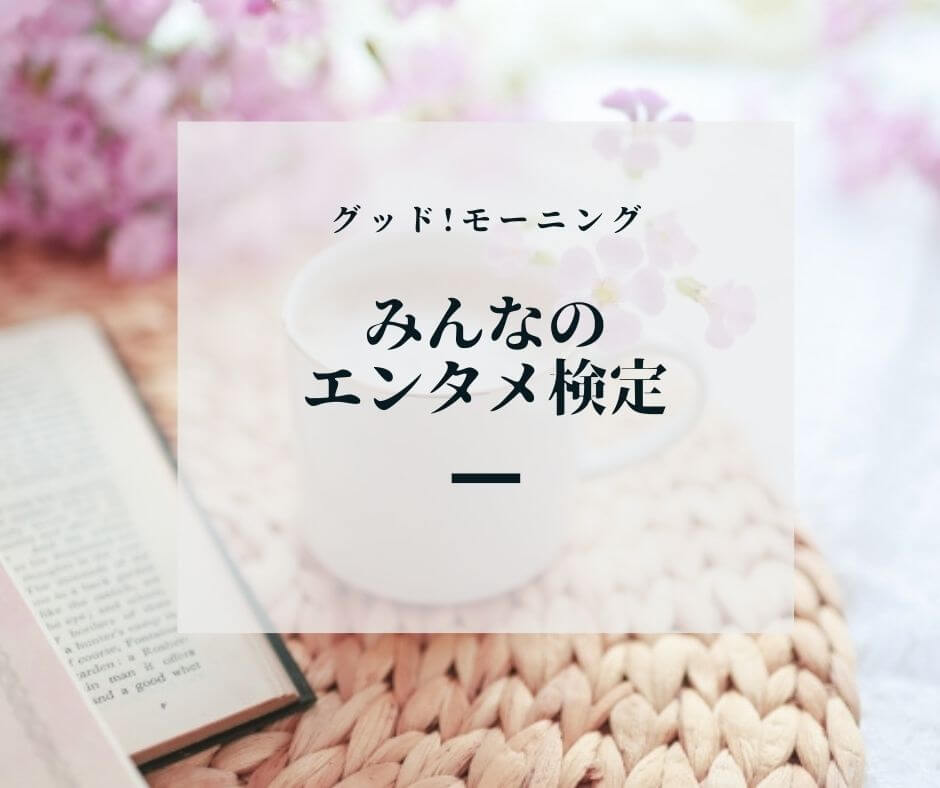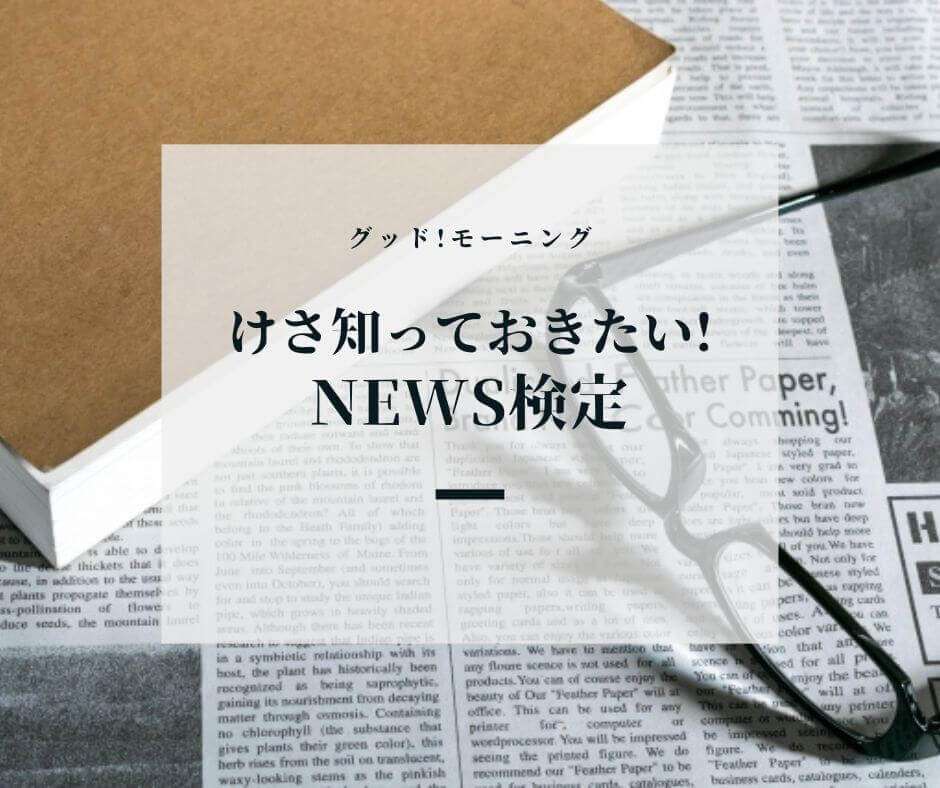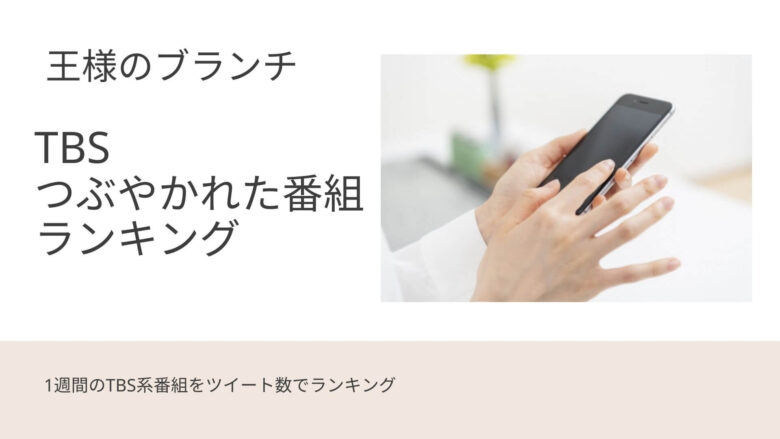江戸時代 「大掃除」の後 何をした?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
*正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。
*解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。
ことば検定 問題
きょうは12月の金曜日ですから、職場や仲間内で忘年会という人も多いかもしれないです。
調査によると、職場の忘年会について参加する前は「面倒」という人は8割近くいるのですが、行ってみたら「楽しかった」という感想を持った人が、その内の65%だったそうです。
こういう忘年会ではねぎらいの言葉がかけられることがあります。
「ねぎらう」を漢字で書くと「労う」です。
送りがなを「労る」とすると「いたわる」と読みます。
この2つは絶対に使う相手を間違えてはいけない言葉です。
「労る」は目上の人に使う言葉で、「労う」は部下をねぎらうなどと目下の相手に使うのが一般的です。
江戸時代は年末の大掃除の後、宴会でねぎらう文化があったといいますが、今日はその際やってきたことは何かという問題です。
江戸時代 「大掃除」の後 何をした?
青 -胴上げ
赤 -三三七拍子
緑 -嗚呼、沖田
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -胴上げ
<今日の緑のボケ>
「おおそうじ」ではなく「おー 総司(Oh 総司)」
ことば検定 解説
きょうの解説
かつて12月13日には「すす掃き」と言って、すすやホコリを払い清める習慣がありました。
このタイミングにやるのは、お正月の神様を迎えるためというのが、昔の理由として一番多かったようです。
普段は手の届かないようなところまでやるのが恒例で、江戸時代には公家も武家も庶民たちもそれぞれが行っていました。
皆で協力して行うので、終わるとお酒と御馳走が振舞われたそうです。
当時の絵を見てみると、とても楽しそうです。
掃除が終わって火鉢らしきものを囲んで楽しみな宴会が始まっている風景が描かれています。
そばやクジラ汁などが出たそうです。
そして今日の答え「胴上げ」も絵に描かれています。
すす掃きが終わると祝儀と称して、面白半分に胴上げをする習慣があったそうです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマーク
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する
*クイズ文の前後に見聞録と入れると見つかりやすくなるかもしれません
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法