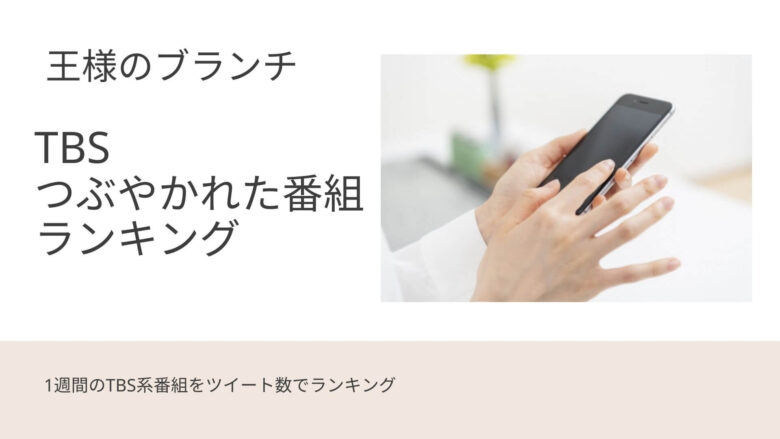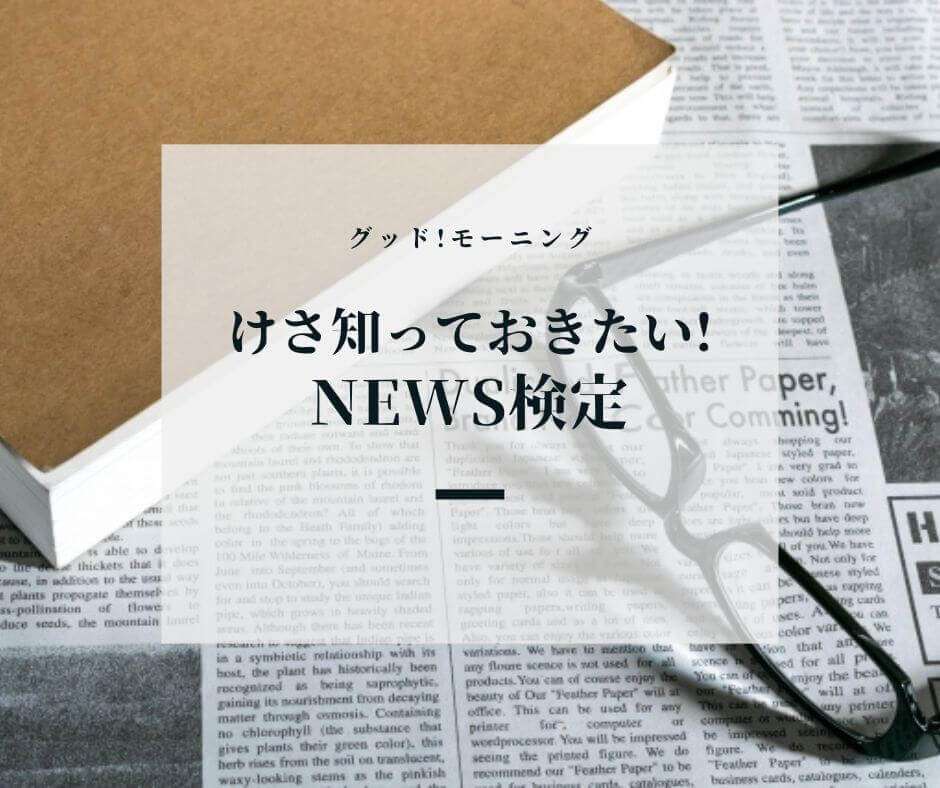「暑中見舞い」元々はどんな風習?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
*正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。
ことば検定 問題
今日6月15日は、昭和25年に初めて暑中見舞いに限定した郵便はがきが発売された日です。
暑中見舞いは二十四節気の小暑から立秋の前日(2024年は7月6日~8月6日)までに送るものとされています。
今はもう無くなりましたが、暑中見舞いのはがきには、年賀はがきのようにくじが付いていて当たるとプレゼントがもらえるようになっていた時期もあります。
「かもめ~る」という名前で売られました。(2020年度廃止)
今日は、その「暑中見舞い」は元々どんな風習だったのかという問題です。
「暑中見舞い」元々はどんな風習?
青 -納涼の祭り
赤 -祖先の霊にお供え
緑 -頻繁に婚活
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -祖先の霊にお供え
ことば検定 解説
きょうの解説
「暑中見舞い」の手紙やはがきを送るようになったのは、明治時代からです。
郵便制度が始まったことが背景にあります。
明治4年に郵便事業は始まりました。
そして、もっと古い江戸時代だと、手紙ではなく相手のところへ贈り物を持って直接訪問するのが「暑中見舞い」でした。
主に、お世話になった人に贈る風習でした。
今でも初夏にお世話になった人に、贈り物をする習慣「お中元」があります。
地域によって贈る時期は多少違うようですが、6月終わりからお盆までに贈ります。
そして、江戸時代に「暑中見舞い」として贈り物を贈る習慣は、お盆に里帰りしたときに品物をお供えする習慣が起源になっていました。
主に、祖先の霊にお供えする風習だったのが、お世話になった人に贈り物を贈るように変わり、その後 手紙やはがきの形に簡素化されたのです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマーク
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する
*クイズ文の前後に見聞録と入れると見つかりやすくなるかもしれません
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法