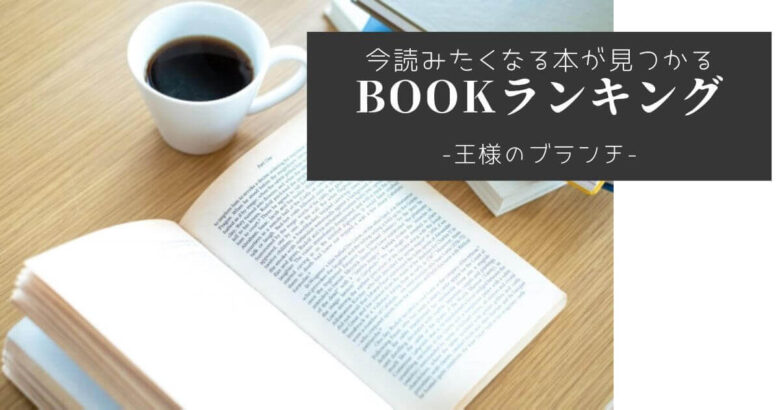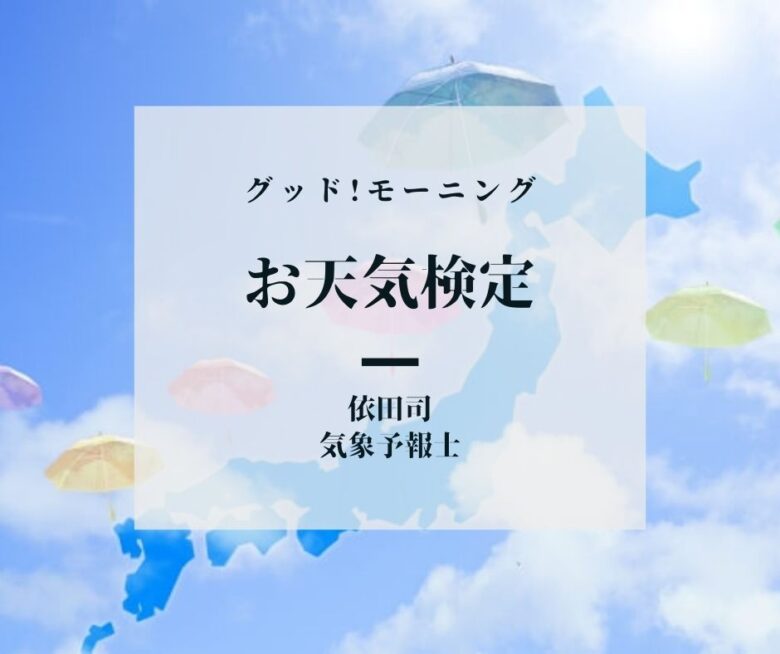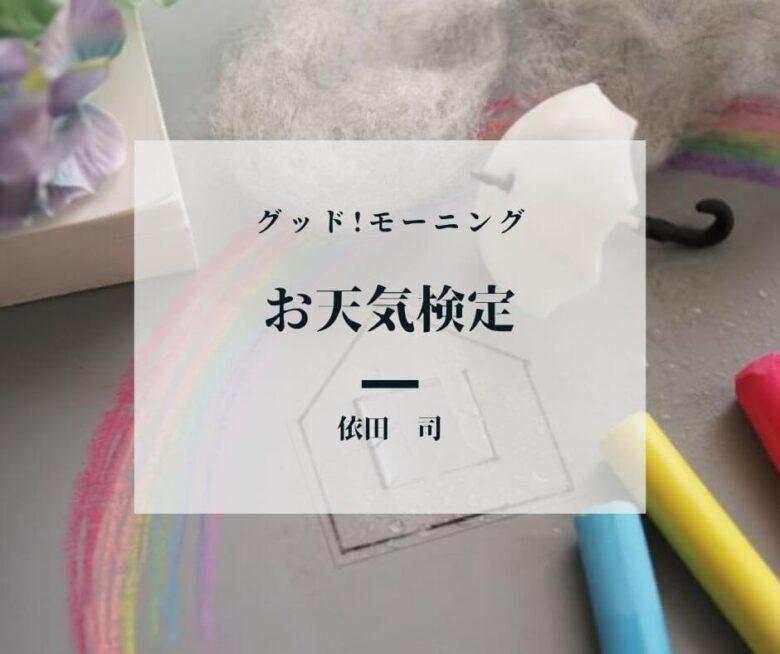「のろま」有力な由来は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
*正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。
ことば検定 問題
今日5月23日は、アメリカの保護団体が制定した「世界カメの日」です。
「鶴は千年 亀は万年」という言葉は、長寿で縁起がいいことを指します。
この言葉が元になって、亀の年を鶴が羨むという言葉もあります。
鶴も長寿なのに、さらなる長寿を羨ましがるということで、欲に限りのない事の例えとして使われます。
卵を産むときに涙を流す亀と言えば「ウミガメ」ですが、実際ウミガメの涙は感情には関係なく出るもので、海水やえさから取りすぎた塩分を体から出しているんだそうです。
カメは地上でゆっくりと動きますが、そんな風に動きが遅いことを「のろま」と言います。
そこで、この「のろま」の由来で有力なものは何かという問題です。
「のろま」有力な由来は?
青 -遅い馬
赤 -人の名前
緑 -宝の地図否定
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -人の名前
ことば検定 解説
きょうの解説
「のろま」は漢字で、愚鈍の鈍の字を書くこともあり、"愚鈍なこと""気がきかないこと"などを指します。
そして「のろま色」という色もあり、青黒い色だそうです。
これはもともと「のろま」と呼ばれていた「のろま人形」が青黒かったことに由来します。
「のろま人形」は江戸時代から人形芝居に使われたのですが、顔が青黒いものがあったのです。
今でも、新潟の佐渡島に残っているそうです。
お祭りの余興に神社やお寺で行われたのですが、愚鈍で滑稽な役だったのです。
この人形は「のろま」という言葉の由来として有力です。
野呂松勘兵衛という人形遣いが始めたことから、「のろま人形」と呼ばれるようになりました。
庶民に大人気だったようです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマーク
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する
*クイズ文の前後に見聞録と入れると見つかりやすくなるかもしれません
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法