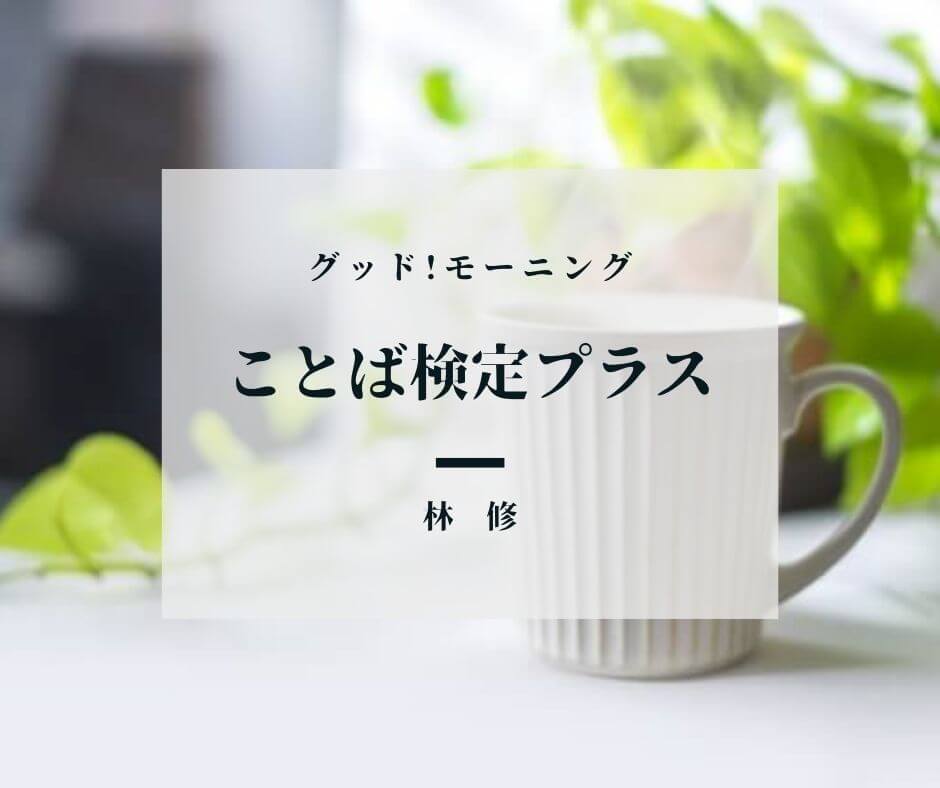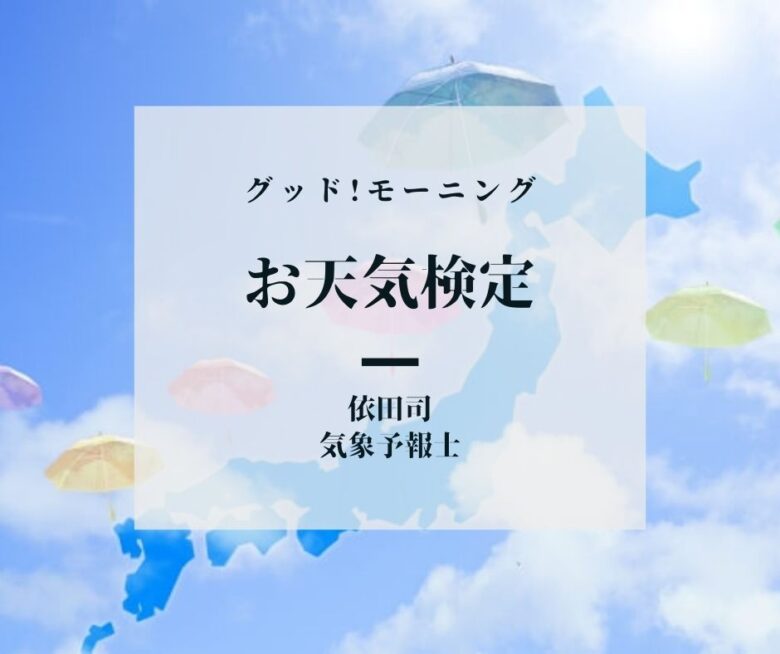「城攻め」が由来の言葉は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう8月28日は、広島・福山市にある福山城の築城記念日です。
福山城の天守は復元されたものですが、記録に基づいて忠実に壁は白と黒の二色になっています。
これはデザインで塗り分けたのではなく、黒い壁には鉄板が貼られていて、この特徴を持つお城はここだけだそうです。
鉄板を使った理由は風や雨への備えのほか、城の防御力を高めるためだとも言われていますが、、貼っていない面もあります。
鉄板は北の壁だけで、他の3方向は内堀と外堀で守りを固めていました。
北側には山があって堀が作れなかったため、鉄板で防御したのではないかと言われています。
そして、福山城は山陽新幹線で駅のホームから城を見ることができます。
石垣のすぐ脇を線路が通っていますが、線路があった場所に江戸時代は内堀で水が張られていた場所です。
今日は次のうち「城攻め」が由来の言葉はどれかという問題です。
「城攻め」が由来の言葉は?
青 -剣幕
赤 -埋め草
緑 -羊研究会
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -埋め草
| <今日の緑のボケ> 「しろぜめ」ではなく「知ろうぜメェ~」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「因縁」と書いて「いんねん」と読みますが、後ろの字「縁」だけだと「えん」と読み、「ねん」とは読みません。
2つの漢字が組み合わされると「因縁(いんねん)」と読みますが、これは「連声(れんじょう)」といって、前の言葉の子音によって後ろの言葉の読み方が変化する現象です。
この「連声」になっていると言われているのが、青の選択肢「剣幕」です。
しかし、「幕」は一字でも「まく」と読みます。
どういうことかと言うと、元々は「険悪」が連声して「剣幕」になったのではないかと言われているのです。
ということで、城とは関係ありません。
「埋め草」が「城攻め」由来の言葉となります。
今は新聞や雑誌で余白を埋めるために入れるちょっとした記事のことを言いますが、元々は雑草などの草を指していました。
かつては、城のお堀を埋めるために草を使っていたそうです。
そこから空白を補うという意味ができたようです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法