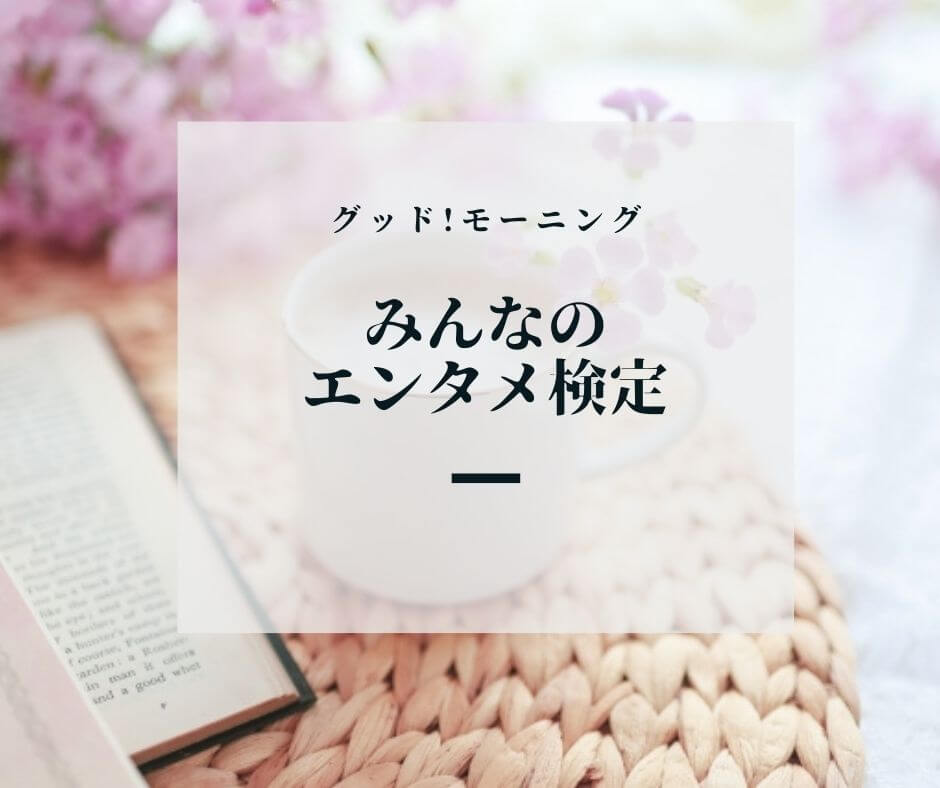「引きずり餅」どんなもの?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
*正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。
*解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。
ことば検定 問題
今年もあと3日になりました。
正月の準備が進んでいるのではないでしょうか?
お正月の餅を年内に用意したいところですが、実は餅つきを避けた方がいいと言われる日があります。
大晦日についたお餅は一夜餅と呼ばれ、葬儀と同じ一夜飾りの意味を持ってしまうため、避けたほうがいいと言われます。
29日も、29という数字が苦・二重苦などに通ずるからだと言われから避けた方いいと言われます。
ただ、一方で「ふく(福)」とも読めるため、地域によっては、むしろ29日を選んで餅つきをするところもあります。
そんなお餅は、古くから正月には欠かせない食べ物で、江戸時代には「引きずり餅」と呼ばれる商売が盛んに行われていました。
今日は、その「引きずり餅」はどんな商売かという問題です。
「引きずり餅」どんなもの?
青 -餅の屋台
赤 -出張餅つき
緑 -公平ではないテスト
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
赤 -出張餅つき
<今日の緑のボケ>
「ひきずりもち」ではなく「ひいきずりー模試」
ことば検定 解説
きょうの解説
お餅は、今はお店で買う人が大半で、家で餅つきをするという人は珍しいかもしれません。
それは江戸時代も同じで、大きな商人の家など一部を除いて、家で餅つきをすることは少なかったようです。
そこで年末の餅の調達に一役買っていたのが、「引きずり餅」です。
その様子は、浮世絵にも描かれています。
お揃いの着物を着た彼らは、年末になると現れる餅つきのスペシャリストでした。
力自慢の男がチームになって、餅つき道具一式を持って、依頼のあった家で餅をついていました。
江戸の町で彼らの威勢のいい掛け声は、景気付けになるとして大人気のサービスだったようです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法