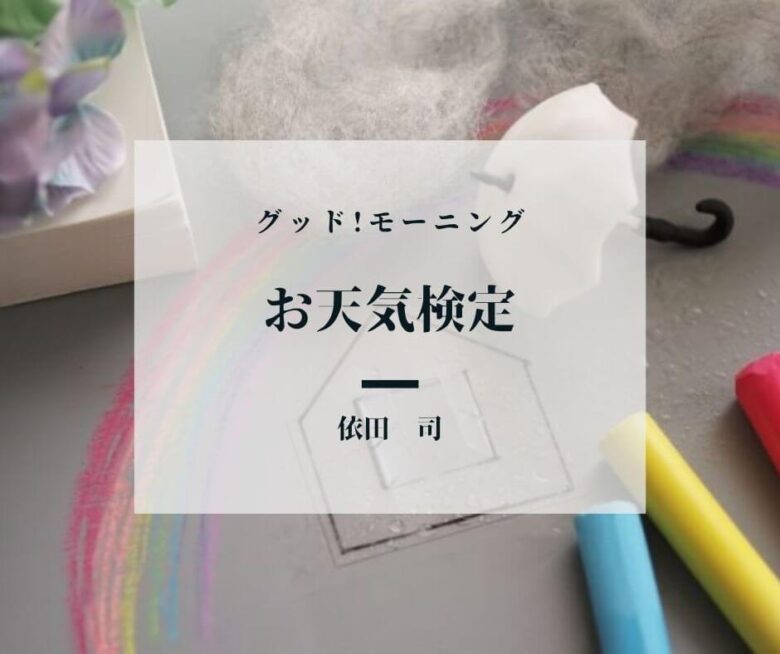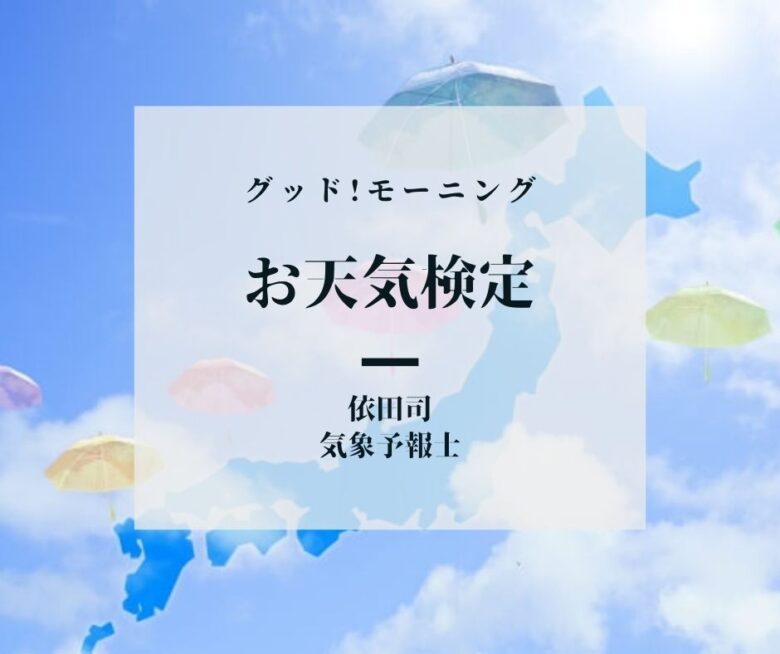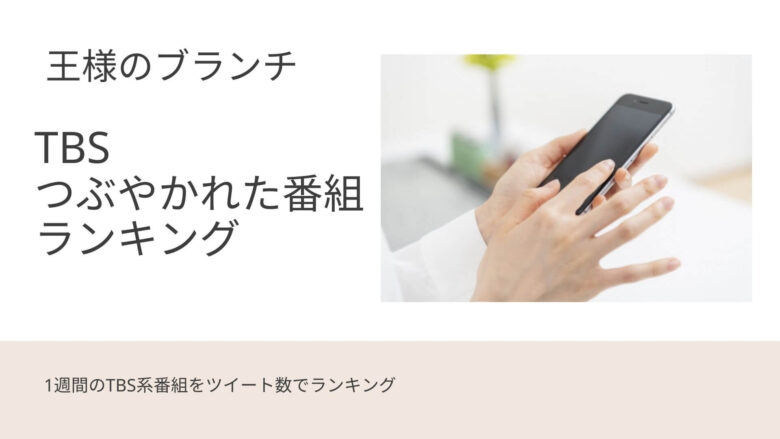「先見の明」の由来は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう9月11日は、1949年に群馬県の岩宿遺跡で発掘調査が始まった日です。
この遺跡の発掘で、日本列島にも旧石器時代に人がいたことがわかり、それは当時の考古学の常識を覆す大発見になりました。
その常識を打ち破ったのは、相澤忠洋さんといいます。
この方は、行商をしながら独学で研究をしていた方です。
その相澤さんが石器を発見したのがきっかけになって、本格的な発掘調査につながりました。
というわけで、今「発見」という言葉が出てきたので、その"見る"という字が入った「先見の明」という言葉について、今日はその由来は何かという問題です。
「先見の明」の由来は?
青 -息子の評価
赤 -流行病
緑 -無茶なはしご酒強要
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -息子の評価
| <今日の緑のボケ> 「せんけんのめい」ではなく「千軒飲めぃ」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「先見の明」とは、ことが起こる前にそれを予見する、見抜く見識のことです。
由来は、中国の歴史書「後漢書」にあり、群雄割拠の時代に魏の基礎を作った曹操の話です。
曹操には、楊脩という部下がいました。
聞かれるであろうことを、先回りして答えを用意しておく大変優秀な部下でしたが、曹操は彼を処刑してしまったのです。
あまりに優れた能力で、きっといつか自分を倒す相手になるだろうと思ってしまったからです。
これは1つの説で、曹操の後継者は長男に決まったのですが、かつてその議論があった時、楊脩は三男を推していました。
曹操としては、後の火種にならないよう楊脩を処刑したという説もあるのです。
いずれにしても、殺された楊脩の父はとても悲しみ、やせ細ってしまいました。
そして、曹操にこんなことを言いました。
「私には金日磾(きんじつてい)のような先見の明がなかった」
ここに「先見の明」という言葉が出てきます。
金日磾というのは、素行が悪い息子を処刑した人物です。
取り返しのつかない大きな過ちを犯す前に、先んじて息子を処刑した金日磾は「先見の明」があったと評価した上で、自分にはそんな才覚がなかったと父親を恥じたといいます。
これが真から出た言葉なのか、それとも息子を処刑した曹操への当てつけだったのかは、実ははっきりしていません。
ただ、このエピソードは、その後 曹操は態度を改めたとして終わっています。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法