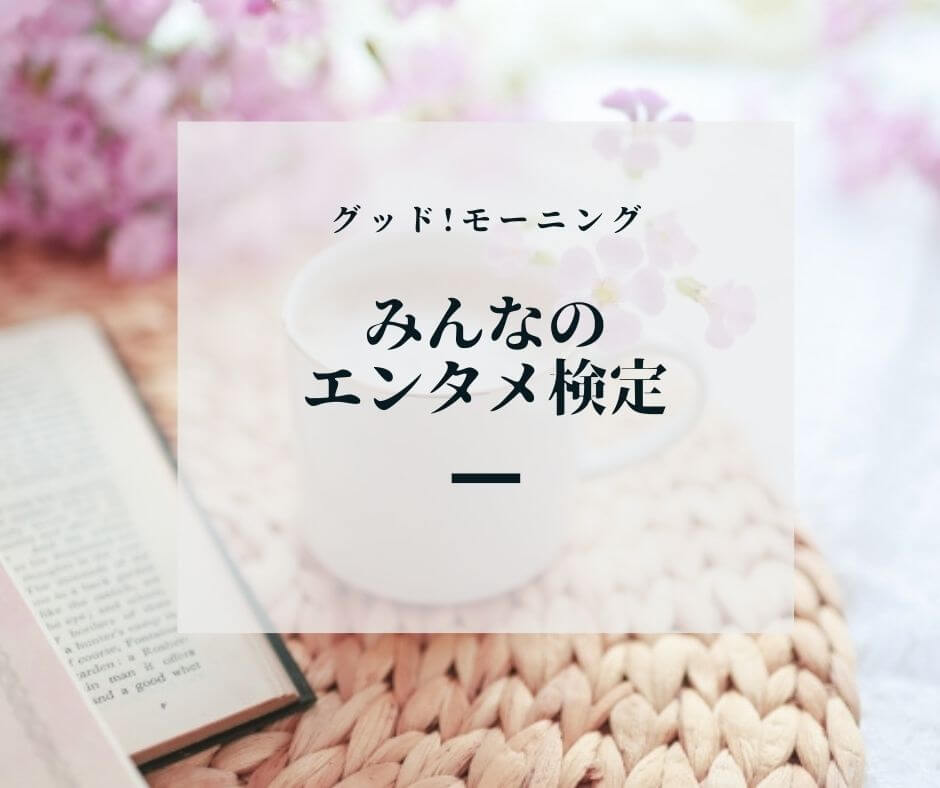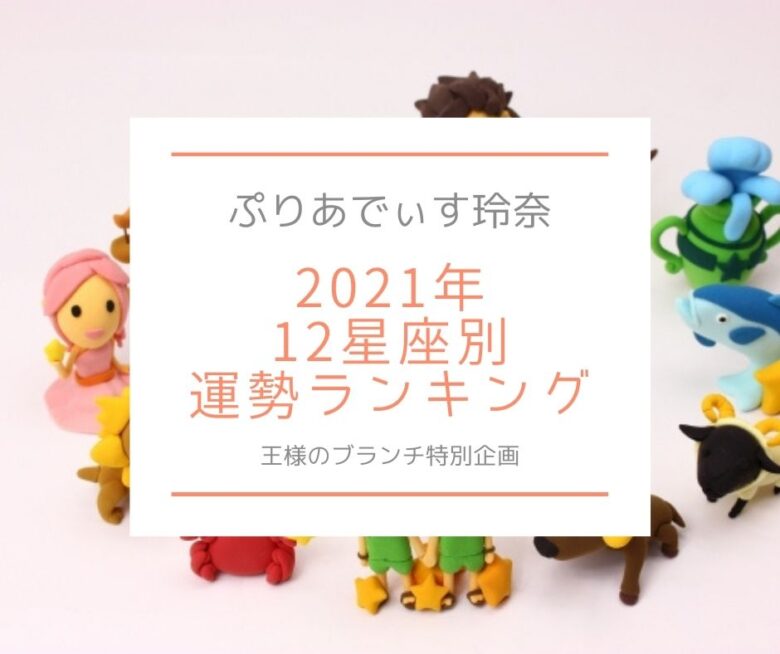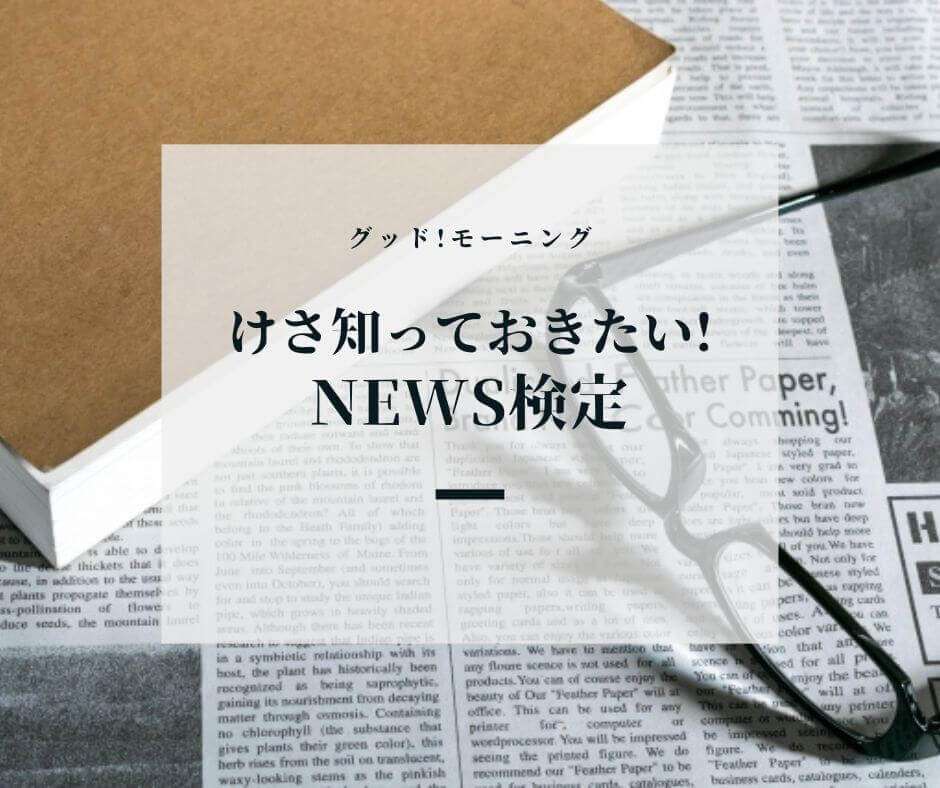「芸術は長く人生は短し」由来は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう8月27日は、1896年に作家の宮沢賢治が生まれた日です。
彼には「注文の多い料理店」「銀河鉄道の夜」などの作品がありますが、「ビジテリアン大祭」という作品もあります。
この「ビジテリアン」とはベジタリアンのことで、この話の設定は、外国の小さな村で世界中から菜食主義者の代表が集まる祭典が開かれ、そこに日本から主人公が出席するというものです。
その祭典では菜食主義について激論が交わされるのですが、実は賢治自身 21歳からベジタリアンだったようです。
とは言っても、他の人と食事をする時には肉や魚を食べたこともあったようです。
この小説は賢治の死後に発表されましたが、生前出版された彼の本は「春と修羅」と「注文の多い料理店」のたった2冊しか生前には出版されなかったのです。
死後に、これほど有名な作家になるとは思わなかったでしょうね。
優れた芸術作品は、作者が亡くなった後も長く残るという意味の「芸術は長く人生は短し」という言葉があります。
そこで今日は、この言葉の由来は何かという問題です。
「芸術は長く人生は短し」由来は?
青 -医術
赤 -輪廻転生
緑 -継いだのに実権は親
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -医術
| <今日の緑のボケ> 「げいじゅつはながくじんせいはみじかし」ではなく「現実は名隠し 院政は身近に」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「芸術は長く人生は短し」は、元々はラテン語で「Ars longa,vita brevis」と書きます。
「Ars(アルス)」を英語にすると「art」となり、"芸術"と訳されることが多いのですが、語源はラテン語の「Ars」で"技術・技能"のことです。
この言葉の生みの親は、今から約2500年前の古代ギリシャで活躍したヒポクラテスです。
魔術と自然現象の区別がつかなかったりすることがあった時代でした。
そんな中、ヒポクラテスは観察や経験を重んじることで、今につながる大きな功績を残したのです。
医学の祖と呼ばれるヒポクラテスの言葉「芸術は長く人生は短し」は、人の一生は短いが技術は深遠で極めがたいものであるから、医を学ぶものは怠らず励むべきであるという教えでした。
これが転じて、芸術分野に対して言われるようになったのです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法