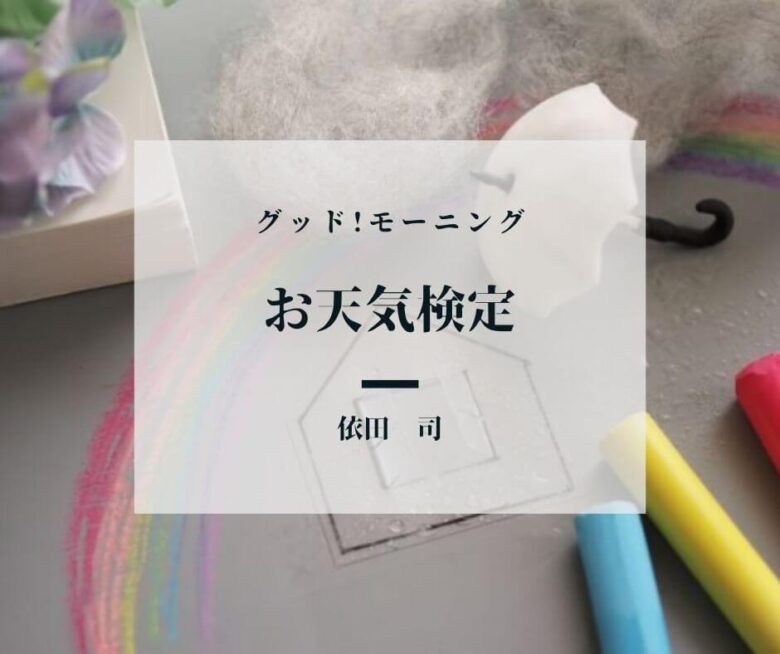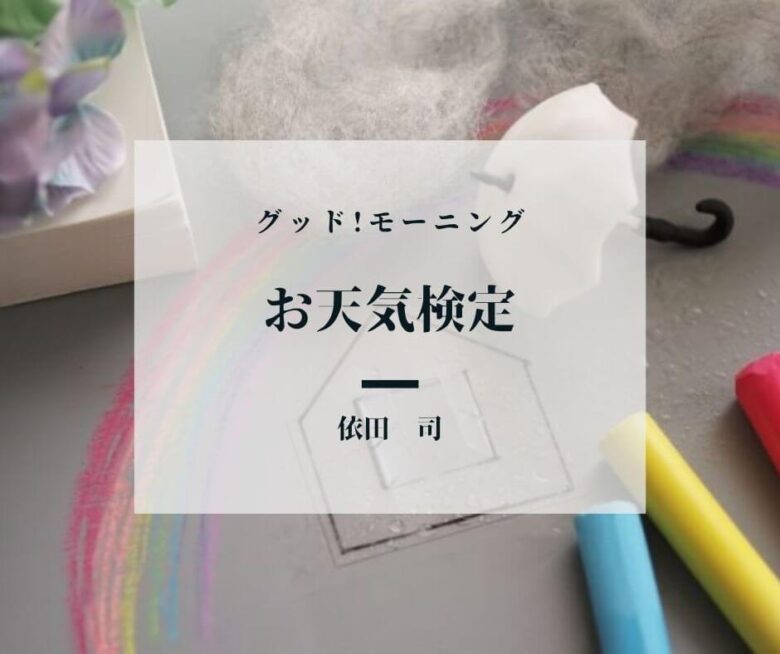北海道「木彫りの熊」戦前のブームきっかけは?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
| *正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう7月17日は、1869(明治2)年に探検家の松浦武四郎が、明治政府に「北加伊道」という名前を提案した日です。
今の「北海道」と「加伊」の部分が違います。
この「加伊」はアイヌの古い言葉で"この地に生まれた人"という意味があるそうですが、明治政府が漢字を「海」に変更し「北海道」という地名が決まりました。
松浦武四郎は6回の探検で、北海道の地図の他、アイヌ民族の姿や松前藩による支配の実態など、見たもの聞いたことを詳細に記録していました。
のちにこれを出版し、人々に広く「北海道」が知られるようになりました。
北海道のお土産といえば、メロンとか海鮮など美味しいもの沢山ありますが、昔とても流行したのが「木彫りの熊」です。
戦前と戦後にそれぞれブームになったのですが、今日はその戦前の最初のブームは何がきっかけで起きたかという問題です。
北海道「木彫りの熊」戦前のブームきっかけは?
青 -海外旅行
赤 -美術の授業
緑 -ヤミ金撲滅隊作ろう
|
「ことば検定」の解答を速報しています |
ことば検定 答え
青 -海外旅行
| <今日の緑のボケ> 「きぼりのくま」ではなく「禁!暴利NO!組まん?」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
北海道の「木彫りの熊」は八雲町というところが発祥です。
ここには熱田神宮の唯一の分社である八雲神社がありますが、熱田神宮のある名古屋と八雲町は深いつながりがあります。
江戸時代に尾張を治めていた大名といえば尾張徳川家ですが、八雲町はその尾張徳川家が開墾した町なのです。
江戸幕府が倒れて明治時代になると、職を失った人がたくさん出ました。
そうした無職になった武士を集団移住させたのです。
ここで「木彫りの熊」を作るようになったのが大正時代で、当時の尾張徳川家の当主・徳川義親さんが発案しました。
義親さんは旅行でスイスに行ったとき、木彫りの熊を見つけそれを買って帰り、八雲の人に農作業の合間の副業として「木彫りの熊」を作ることを勧め、これがきっかけで戦前のブームになりました。
ちなみに、鮭を咥えた熊はアイヌの方が多く作り、戦後にブームになったそうです。
前回の問題

ここを素早く見つけるコツで~す
①「見聞録 KENBUNROKU」をブックマークしていただくことを推奨します。
② Googleなどの検索エンジンで「クイズの文章」で検索する方法3選
*クイズ文の前に見聞録と入れると見つかりやすくなることが多いです。
*クイズ文に?ありで検索して見つからなくても、?をとると見つかることがあります。
*クイズ文に?なしで検索して見つからなくても、?を付けると見つかることもあります。
(注) 当ブログを転載している海外スパムサイトにご注意ください
今月のプレゼントと応募方法